昔、1人の旅のお坊さんが、夕暮れ時にある村を訪れた。
もう日も暮れかかっているので、今日はこの村で一晩の宿を借りようと一軒の家の前に来た。ところが、この村の掟では、用心のため旅人を泊めないことになっていたのだ。仕方がないので、ここの家の主人は、峠の中ほどにある化け物が出ると言われるやぶれ寺に泊まるようお坊さんに言い、何かあったら鐘を突いて知らせるように伝えた。
さて、夜のお勤めも終わりお坊さんが本堂で寝ていると、真夜中になり何やらドシン!!ドシン!!と大きな音がする。お坊さんが起きてみると、なんとそこには茶つぼが飛び跳ねていたのだ。お坊さんは驚いて、「そちは、なんじゃい?なんじゃいのぅ?」と問いただした。
すると茶つぼは、「ワシは寺の茶つぼじゃ。そっちはなんじゃい?なんじゃいのぅ?」と答える。お坊さんはまた言う。「ワシは、寺の和尚じゃ。そっちはなんじゃい?なんじゃいのぅ?」こんな押し問答を続けたあげく、茶つぼは和尚さんに向かって体当たりをしてきたので、2人は取っ組み合いの喧嘩になった。ところが、夜明けになり一番鳥が鳴くと、茶つぼは慌てて縁の下に隠れてしまい姿を見せなくなった。
そこでお坊さんは鐘を突いて村の衆を呼び集めた。村で一番力持ちの為どん(ためどん)が縁の下に入って見てみると、そこにはお坊さんが思ったとおり大きな茶つぼがあった。そして茶つぼを開けてみれば、なんと茶つぼの中からは先代の住職が隠した小判がたくさん出てきたのだ。
人知れず寺の縁の下に隠された小判が、誰かに使ってもらいたくて化けて出たのだった。村人はその後、茶つぼから出てきた小判を使ってお寺を建て直し、この旅のお坊さんを住職に招いた。そしてお坊さんは中興開山の祖となり、寺は末永く栄えたそうだ。
(投稿者: やっさん 投稿日時 2011-11-16 11:49)
| ナレーション | 市原悦子 |
| 出典 | 杉原丈夫(未来社刊)より |
| 出典詳細 | 越前の民話 第一集(日本の民話44),杉原丈夫、石崎直義,未来社,1968年04月30日,原題「茶つぼ」,話者「山口久三」 |
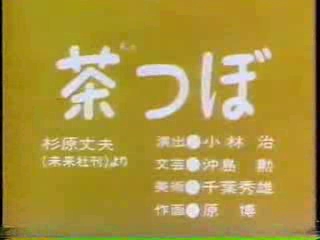


| このお話の評価 |  8.00 (投票数 4) ⇒投票する 8.00 (投票数 4) ⇒投票する |
⇒ 全スレッド一覧