昔ある村に、直吉という一人暮らしの漁師がいました。月のない暗い夜に、かがり火をたきながらシラウオ漁をしていると、沖の方から沢山の人の掛け声が聞こえてきました。
きっと何か重いものを運んでいると思った直吉は、手伝うために着物を脱いで海に飛び込みました。そして声のする方へ泳いでいくと、大勢の人たちが泳ぎながら大きな流木を押し運んでいました。
きっと難破した船の人たちだろう、と思った直吉は、さっそく流木を押して島まで押し上げてあげました。岸に上がった直吉が、あらためて人々の顔を見ると、それは男か女か人間か化け物かわからない、真っ黒い疫病神が立っていました。
「この島に熱病を運んできた」と言う厄病神は、流木運びを手伝ってくれた直吉に「夜鳥が鳴いたら杵(きね)で臼(うす)を叩きなさい、その音がする家には熱病を持って行かないから」と言い残し、すぅっと消えていきました。
これを聞いた直吉は、大急ぎで村の総代の家に村人たちを集めて、今までの事を全部話しました。そして村人たちは、夜鳥が鳴くとどこの家でも杵で臼をたたき、厄病神が家に来るのを阻止しました。結局、疫病神たちはどこの家にも熱病を持って行けず、やがて夜明けとともに大慌てで海の向こうへ逃げていきました。
この事で村人たちから感謝された直吉は、あちこちから良い縁談が舞い込んで、めでたく所帯を持つことができました。
(紅子 2012-4-30 0:54)
| ナレーション | 市原悦子 |
| 出典 | 川崎大治(童心社刊)より |
| 出典詳細 | 日本のおばけ話(川崎大治 民話選2),川崎大治,童心社,1969年3月5日,原題「厄病鳥」 |
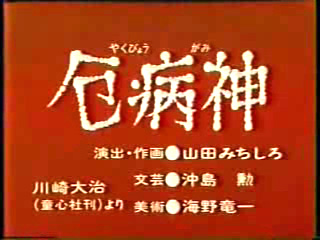


| このお話の評価 |  8.13 (投票数 8) ⇒投票する 8.13 (投票数 8) ⇒投票する |
⇒ 全スレッド一覧