情報の掲載されているページはこちらです。(本文に戻る)byまんが日本昔ばなし〜データベース〜[印刷用画面]
豆の木だいこ(まめのきだいこ)
| 放送回 | No.0814(0512-A) |
| 放送日 | 1985年09月07日(昭和60年09月07日) |
| 出典 | 谷口茂雄「滋賀県の民話」(偕成社刊)より |
| クレジット | 演出:山田みちしろ 文芸:沖島勲 美術:小山哲生 作画:宍戸久美子 |
| ナレーション | 市原悦子 |
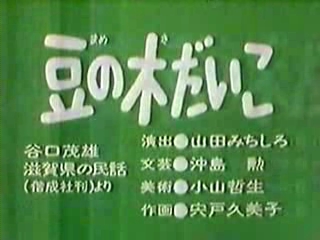
|

|

|
あらすじ
昔、秦荘村(はたしょうむら)の金剛輪寺に、和尚さんと小僧さんがいました。この頃の村は、雨が続いたり日照りが続いたりして作物が十分に育たず、村人たちはいつもひもじい思いをしていました。
ある時、和尚さんは「村人にソラマメを作らせよう」と、ソラマメの種をもらいに西の村へ旅立ちました。日照りの中を歩き続け、ようやく西の村にたどり着いた和尚さんは、おたふく豆のように大きく立派なソラマメの種をもらう事ができました。お寺に帰った和尚さんは、秋になってから植え付けようと考え、押し入れの箱の中に大切に保管しておきました。
ところがある日、腹をすかせた小僧さんがこのソラマメを火で炒って全部食べてしまいました。秋になってソラマメがなくなっている事に気が付いた和尚さんは、村人たちの大切なソラマメだった事を小僧さんに言って聞かせました。悪い事をしたと思った小僧さんは「一粒でもいいから残っていないだろうか」と探してみると、一粒だけ薪(まき)の下に落ちていました。
小僧さんは一粒のソラマメをお寺の庭に蒔いて、毎日々神様にお願いしながら大切にお世話をしました。やがて春になりソラマメから芽が出てきて、ぐんぐん大きく育ち、幹は二人でも抱えきれない程の太さまで育ちました。この豆の木から採れたソラマメを村人たちにも分けてあげて、みんなでソラマメを蒔くとまた沢山の豆が採れました。
このソラマメのおかげで、食べ物に困る事が無くなり感謝した村人たちは、お寺のソラマメの木で太鼓を作りました。今でもこの太鼓は金剛輪寺に残っていて、この話を大切に語り継いでいます。
(紅子 2012-2-11 20:00)
| 地図:金剛輪寺 |